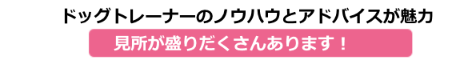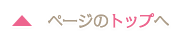グレーハウンドのしつけのコツ14選!特性の理解が大切

イタリアングレーハウンドのしつけに関しては、「繊細だから厳しく叱らない方がよい」「運動が足りないと問題行動が出やすい」など意見が分かれており、どの方法が正しいのか混乱してしまう飼い主も少なくありません。この犬種は感受性が高く、環境の影響を受けやすいため、一律のしつけ方法ではうまくいかない場合もあります。そのため、個々の性格に寄り添いながら信頼関係を築いていく姿勢が重要だといえるでしょう。
そこで以下にその詳細についてまとめてみました。
■参考情報
経験豊富なプロが開発した犬のしつけ教材お勧めランキング3
これらは犬のしつけのプロが長年にわたり現場で培ったノウハウが凝縮されている血と涙と汗の結晶ともいえる傑作揃いです。まだまだ他にも素晴らしい教材が盛りだくさんですし、ランキング付けの理由や犬のしつけ教材選び重要ポイントなども説明しているのでお見逃しなく!
⇒他の犬のしつけ教材もチェックして極秘ノウハウを根こそぎ継承したい人はこちら
| 順位 | 教材名 | 概要 |
|---|---|---|
| 1位 | 藤井聡の犬のしつけ法 | 日本一のカリスマ訓練士の藤井聡の秘伝ノウハウ |
| 2位 | イヌバーシティ | 30,000頭の犬に囲まれて誕生したしつけ術 |
| 3位 | 愛の家庭犬しつけ法 | 狩野誠の問題行動解決特化型しつけ法 |
これらは犬のしつけのプロが長年にわたり現場で培ったノウハウが凝縮されている血と涙と汗の結晶ともいえる傑作揃いです。まだまだ他にも素晴らしい教材が盛りだくさんですし、ランキング付けの理由や犬のしつけ教材選び重要ポイントなども説明しているのでお見逃しなく!
⇒他の犬のしつけ教材もチェックして極秘ノウハウを根こそぎ継承したい人はこちら
目次
イタリアングレーハウンドの特徴
イタリアングレーハウンドは、しなやかな体と優雅な動きが魅力の小型犬です。古代ローマ時代から愛されていた歴史があり、その美しい姿はまるで芸術作品のようです。体は細身で筋肉質、特に足が長くスタイルがよいため、走る姿は風を切るように軽やかです。短毛で毛並みも滑らかなので、手入れは比較的簡単ですが、寒さには非常に弱く、気温の低い日には服を着せて体温管理が必要です。
性格は一見クールに見えることもありますが、飼い主との信頼関係ができるととても甘えん坊な一面を見せます。家の中では静かでおとなしく過ごすことが多いものの、十分な運動ができていないとストレスをためてしまうため、毎日の散歩や遊びの時間が欠かせません。
また、繊細な心を持っているため、急な音や環境の変化には敏感に反応します。叱るよりも褒めて育てるスタイルが向いており、丁寧で穏やかな接し方が信頼を築く鍵になります。見た目の美しさと内面の繊細さを併せ持つこの犬種は、深い愛情と時間をかけて向き合うことで、かけがえのないパートナーとなってくれます。
イタリアングレーハウンドのしつけのコツ14選
イタリアングレーハウンドは繊細な性格で、人の声のトーンや感情に敏感に反応します。そのため、しつけの方法を誤ると信頼関係を築けず、かえって問題行動を引き起こすこともあります。だからこそ、特性に合ったしつけのコツを事前に理解しておくことが、安心して暮らすためにとても重要なのです。
そこでイタリアングレーハウンドのしつけのコツについて解説します。
例えば、何かいたずらをしたときでも感情的にならず、冷静に対応することが大切です。声を荒げるより、「だめだよ」と静かに伝える方が、犬は安心して行動を見直すことができます。特にこの犬種は、叱られることよりも“飼い主に嫌われたかもしれない”と感じる方がストレスになるため、信頼を損なわない言い方を意識しましょう。
また、褒めるときも優しいトーンで「いい子だね」と声をかけることで、犬は“何が正しい行動なのか”を理解しやすくなります。言葉の内容よりも、声の調子が伝えるメッセージの大部分を占めていると言っても過言ではありません。
日々の接し方ひとつで、イタリアングレーハウンドは驚くほど素直に育っていきます。優しい口調を意識することは、単なるしつけのテクニックではなく、犬との信頼を育む第一歩なのです。
たとえば、トイレがうまくできたときや、指示通りに動けたときなど、小さな成功でも「よくできたね」「すごいね」と声をかけてあげましょう。このような前向きなフィードバックは、イタリアングレーハウンドにとってご褒美のようなものであり、「こうすれば飼い主が喜ぶ」と理解しやすくなるのです。
一方で、失敗したときに大声で怒ってしまうと、「何が悪かったのか」が分からず混乱してしまいます。この混乱が積み重なると、不安や不信感を抱くようになり、かえって問題行動が増えることもあるため注意が必要です。
褒め方のコツは、タイミングを逃さず、その場ですぐに反応してあげること。ごほうびのおやつを活用しても構いませんが、言葉や笑顔だけでも十分に効果があります。
たとえば「おすわり」や「まて」などの基本指示を教える際にも、10分以上かけて続けてしまうと飽きたり疲れたりしてしまい、しつけそのものが嫌なものとして記憶されてしまう可能性があります。それよりも、朝の散歩前や食事前など、日常の合間に1?2分だけ練習する方が、楽しみながら身につけることができます。
この「こまめに」という姿勢は、犬にとっても「これは日常の一部なんだ」と感じさせる効果があり、特別な負担をかけずに自然に学ばせることができます。また、トレーニングのたびに褒めることを忘れずに行えば、ポジティブな記憶が積み重なり、自発的に指示を聞くようになっていくでしょう。
たとえば、ソファに乗ってはいけないというルールを決めたなら、誰が相手でも一貫してそのルールを守らせる必要があります。家族の一人が「今日は特別」と許してしまうと、犬はルールを覚えるどころか、“気分次第で変わるもの”と認識してしまい、しつけの意味が薄れてしまうのです。
イタリアングレーハウンドは人懐っこく、飼い主の喜ぶ顔を見るのが好きなタイプですが、その分、曖昧な指示や行動には戸惑いや不安を感じます。だからこそ、どんなときでも“ダメなものはダメ”と一貫した態度をとることが、犬に安心感と信頼を与えることにつながるのです。
また、家族全員が同じルールを共有して守ることも忘れてはいけません。一人だけが違う対応をすると、それだけで学習がリセットされることもあります。ルールの一貫性は、犬との良い関係を築くうえでの土台となる大切なポイントなのです。
社会化が不十分なまま成犬になると、来客に対して吠えたり、外で他の犬とすれ違うだけで過剰に反応したりと、生活の中で不安が多くなってしまいます。逆に、子犬のうちから“これは怖くない”“これは楽しい”というポジティブな経験を積んでおくことで、自信のある落ち着いた性格に育ちやすくなります。
例えば、抱っこして近所を歩いたり、優しい友人に触れてもらったり、日常の生活音に慣らしたりと、できるだけ多様な刺激を「楽しい体験」として結びつけていくことがポイントです。もちろん、無理やり怖がる状況に置くのではなく、愛犬のペースを尊重しながら少しずつ進めることが大切です。
社会化は一度に終わるものではありませんが、特に生後3ヶ月前後の“吸収力が高い時期”に積極的に取り組むことで、その後のしつけや生活のしやすさに大きな違いが出てきます。安心して過ごせる土台をつくるという意味でも、早期の社会化はしつけの基本中の基本といえるでしょう。
たとえば、掃除機の音やドライヤーの風、車の通行音など、家庭内外にある「よくあるけれど不快に感じやすい音」は、子犬の頃から少しずつ聞かせて慣らしていくと安心です。最初から大きな音を長時間聞かせるのではなく、小さな音量から始めて、徐々に音の大きさや時間を増やすようにします。
また、散歩コースを時々変えてみるのも効果的です。はじめての道や場所に連れて行くことで、視覚や嗅覚にも刺激が入り、環境の変化に柔軟に対応できるようになります。ただし、無理に引っ張ったり強制的に進めたりすると、かえってトラウマになってしまうことがあるため、犬の様子を見ながらペースを合わせてあげましょう。
例えば、初めてのトレーニングや新しいコマンドを教えるときには、家の中の静かな部屋を選ぶとよいでしょう。外からの騒音や他の犬の声が聞こえる環境だと、イタリアングレーハウンドは不安を感じたり、気が散ってしまったりすることがあります。静かな環境ならば、飼い主の声がはっきりと届き、コミュニケーションが取りやすくなります。
また、落ち着いた場所でトレーニングを繰り返すことで、犬にとって「ここは学びの時間だ」と認識させやすくなります。この習慣づけは、しつけの成功率を高めるだけでなく、犬自身のストレス軽減にもつながります。逆に、騒がしい場所で無理にトレーニングを続けると、犬が疲れてしまい、しつけ自体が嫌いになってしまう恐れもあるため注意が必要です。
さらに、静かな環境でのトレーニングは、イタリアングレーハウンドが持つ繊細な性格に寄り添うという意味でも大切なポイントです。
最初のうちは失敗することも多いですが、そのたびに叱るのではなく、成功したときにしっかりと褒めることがポイントです。例えば、決まった場所で排泄できたら「いい子だね」と優しく声をかけたり、おやつを与えたりしてポジティブな体験と結びつけます。これにより、犬は「ここですると嬉しいことがある」と理解し、トイレの場所を覚えやすくなります。
また、決まった時間にトイレに連れて行く習慣をつけることも重要です。食後や起床後、遊んだあとなど、排泄しやすいタイミングを見極めて声をかけることで、犬のリズムを掴みやすくなります。定期的に声をかけることで、「トイレに行くタイミング」を犬自身が認識できるようになるのです。
イタリアングレーハウンドは精神的な影響を受けやすいため、失敗しても怒らず、落ち着いて対応することが肝心です。飼い主が根気強く続けることで、徐々に正しい場所での排泄が習慣化し、生活の質も向上します。
毎日の散歩は、単に運動するだけでなく、犬にとって新しい刺激や経験を得る大切な時間でもあります。外の世界でさまざまな匂いを嗅ぎ、人や他の犬と触れ合うことで社会性も育まれます。遊びの時間を設けることも同様に重要で、特にボール遊びや軽い引っ張り合いなど、飼い主と一緒に楽しむことで、犬との絆が深まるとともに、良いコミュニケーションのきっかけになります。
イタリアングレーハウンドはその繊細な性格から、不足する刺激に対して敏感に反応することが多いので、遊びや散歩での適度な発散は精神的な安定にもつながります。逆に、運動不足のままだと体力が有り余り、集中力が落ちるため、しつけの効果も半減してしまうことがあります。
また、運動を取り入れたしつけの時間は、犬にとって楽しいだけでなく、学習意欲を高める良い機会にもなります。体を動かしながらのトレーニングは、指示に対する反応も良くなり、無理なくルールを覚えていくことができるでしょう。
まずは数分から始めて、短時間の離れる練習を繰り返します。最初は飼い主の姿が見えなくなるだけでも不安になることがあるので、できるだけ穏やかに出かけるように心がけましょう。飼い主が帰ってきたときは、落ち着いた態度で迎え、過剰に大げさに喜びすぎないことも大切です。そうすることで、犬は「ひとりの時間は特別なものではない」と理解しやすくなります。
また、お留守番中に安心できる環境を整えることも大切です。お気に入りのおもちゃや、安心できるブランケットを用意したり、音楽を流すなどリラックスできる工夫を取り入れましょう。これらは犬の不安を和らげる助けとなります。
例えば、ブラッシングや爪切り、耳掃除などのケアは、体に触れることに慣れていないと抵抗を示すことがあります。しかし、幼いうちから触ることに慣れていれば、こうしたケアもストレスなく受け入れやすくなるため、病気の早期発見や快適な生活に役立ちます。
触れ方のポイントは、無理強いせず、優しい手つきで行うことです。嫌がったら無理に続けず、一旦やめて落ち着かせることを繰り返すことで、犬自身が「触られても怖くない」と理解していきます。また、触れた後には褒めたりおやつをあげたりして、良い経験として結びつけることも効果的です。
さらに、日常生活の中で散歩の前後や遊びの合間など、リラックスしているタイミングに触る習慣をつけると、自然と受け入れやすくなります。イタリアングレーハウンドの繊細な心に配慮しながら、ゆっくり丁寧に慣らしていくことが、信頼関係を深めることにもつながるでしょう。
例えば、新しいことを教えるときやトレーニングをする際に、犬が戸惑ったり怖がったりしている場合は、一旦休憩を挟むなど無理せず様子を見ましょう。無理強いすると犬が嫌悪感を抱き、飼い主の指示を避けるようになる可能性もあります。イタリアングレーハウンドは、安心感を持てる環境でこそ力を発揮し、しつけもスムーズに進みます。
また、叱る際も強く叱りつけるのではなく、なぜダメなのかを静かに伝えることが大切です。怒鳴ったり身体的に制止することは逆効果となり、犬の自信を失わせてしまうこともあります。代わりに、良い行動をしたときはたっぷり褒めて、ポジティブな関係を築くことを心がけましょう。
しつけは長期戦であり、一気に成果を求めすぎないこともポイントです。イタリアングレーハウンドの気持ちに寄り添いながら、ゆっくりと根気よく続けることが、最終的には良い結果をもたらします。
陽性強化とは、犬が望ましい行動をした際に褒めたりご褒美を与えたりして、その行動を強化するトレーニング方法です。クリッカーはそのタイミングを正確に知らせるツールとして非常に優秀で、「今の行動が正解」というサインを瞬時に伝えられるため、イタリアングレーハウンドの理解が早まります。
例えば、「おすわり」ができた瞬間にクリッカーの音を鳴らし、すぐにおやつを与えると、犬は「おすわりをすると良いことがある」と学習しやすくなります。この明確な報酬システムは、叱るしつけとは違い、犬のストレスを減らしながらポジティブに行動を促せるため、信頼関係の構築にも役立ちます。
また、クリッカーは小さな成功体験を積み重ねるのに適しており、複雑なコマンドや新しいトリックを教える際にも有効です。イタリアングレーハウンドの繊細な性格を尊重しつつ、楽しくトレーニングできる環境を作るために、陽性強化ツールの活用はおすすめの方法と言えるでしょう。
例えば、食事の前に「おすわり」をさせる、散歩のときにリードを引っ張らないように声をかける、来客時には落ち着いて挨拶させるなど、日々の行動の中でしつけを取り入れていく方法です。こうした繰り返しの積み重ねが、犬にとって「こうするのが普通」という習慣となり、無理なくルールを守れるようになります。
また、イタリアングレーハウンドは環境の変化や新しい刺激に敏感なため、日常の中で様々な場面を通じて経験を積ませることが精神的な安定にもつながります。たとえば、散歩で通る場所や訪れる人が変わっても、基本的なマナーを守らせる練習をしておくことで、どんな状況でも落ち着いて行動できるようになるのです。
さらに、日常生活でのしつけは、飼い主と犬とのコミュニケーションを深める良い機会でもあります。声のトーンや褒め方を工夫しながら、楽しく続けられることが、イタリアングレーハウンドの信頼と理解を促進します。特別な時間だけでなく、毎日の暮らしの中でしつけを意識的に取り入れることで、より良い関係が築けるでしょう。
優しい口調で指示を出す
この犬種は感受性が高く、人間の声のトーンや表情に敏感に反応する傾向があります。大きな声で叱ると恐怖心を抱き、心を閉ざしてしまうこともあるため、強い言葉よりも落ち着いた優しい声で接する方が信頼関係を築きやすくなります。例えば、何かいたずらをしたときでも感情的にならず、冷静に対応することが大切です。声を荒げるより、「だめだよ」と静かに伝える方が、犬は安心して行動を見直すことができます。特にこの犬種は、叱られることよりも“飼い主に嫌われたかもしれない”と感じる方がストレスになるため、信頼を損なわない言い方を意識しましょう。
また、褒めるときも優しいトーンで「いい子だね」と声をかけることで、犬は“何が正しい行動なのか”を理解しやすくなります。言葉の内容よりも、声の調子が伝えるメッセージの大部分を占めていると言っても過言ではありません。
日々の接し方ひとつで、イタリアングレーハウンドは驚くほど素直に育っていきます。優しい口調を意識することは、単なるしつけのテクニックではなく、犬との信頼を育む第一歩なのです。
褒めて伸ばすしつけを心がける
この犬種は、繊細で賢く、飼い主の感情をよく読み取る能力があります。そのため、厳しく叱るよりも、良い行動をとった瞬間にしっかりと褒めることで、自信を持って学習するようになります。たとえば、トイレがうまくできたときや、指示通りに動けたときなど、小さな成功でも「よくできたね」「すごいね」と声をかけてあげましょう。このような前向きなフィードバックは、イタリアングレーハウンドにとってご褒美のようなものであり、「こうすれば飼い主が喜ぶ」と理解しやすくなるのです。
一方で、失敗したときに大声で怒ってしまうと、「何が悪かったのか」が分からず混乱してしまいます。この混乱が積み重なると、不安や不信感を抱くようになり、かえって問題行動が増えることもあるため注意が必要です。
褒め方のコツは、タイミングを逃さず、その場ですぐに反応してあげること。ごほうびのおやつを活用しても構いませんが、言葉や笑顔だけでも十分に効果があります。
短いトレーニング時間をこまめに行う
この犬種は頭の回転が速く物覚えも良い一方で、集中力が長く続かない傾向があります。そのため、1回あたりの練習時間を数分程度に抑え、1日に何度か繰り返してあげる方が、無理なく学習を進められるのです。たとえば「おすわり」や「まて」などの基本指示を教える際にも、10分以上かけて続けてしまうと飽きたり疲れたりしてしまい、しつけそのものが嫌なものとして記憶されてしまう可能性があります。それよりも、朝の散歩前や食事前など、日常の合間に1?2分だけ練習する方が、楽しみながら身につけることができます。
この「こまめに」という姿勢は、犬にとっても「これは日常の一部なんだ」と感じさせる効果があり、特別な負担をかけずに自然に学ばせることができます。また、トレーニングのたびに褒めることを忘れずに行えば、ポジティブな記憶が積み重なり、自発的に指示を聞くようになっていくでしょう。
決まったルールを一貫して守る
この犬種は繊細で感受性が高いため、飼い主の態度に敏感に反応します。昨日は許されたことが、今日は叱られる――そんな対応の違いがあると混乱し、どう行動すればよいのか分からなくなってしまいます。たとえば、ソファに乗ってはいけないというルールを決めたなら、誰が相手でも一貫してそのルールを守らせる必要があります。家族の一人が「今日は特別」と許してしまうと、犬はルールを覚えるどころか、“気分次第で変わるもの”と認識してしまい、しつけの意味が薄れてしまうのです。
イタリアングレーハウンドは人懐っこく、飼い主の喜ぶ顔を見るのが好きなタイプですが、その分、曖昧な指示や行動には戸惑いや不安を感じます。だからこそ、どんなときでも“ダメなものはダメ”と一貫した態度をとることが、犬に安心感と信頼を与えることにつながるのです。
また、家族全員が同じルールを共有して守ることも忘れてはいけません。一人だけが違う対応をすると、それだけで学習がリセットされることもあります。ルールの一貫性は、犬との良い関係を築くうえでの土台となる大切なポイントなのです。
社会化を早いうちから進める
この犬種は、見た目の気品さとは裏腹に、非常に繊細で警戒心が強い一面を持っています。そのため、子犬の時期にさまざまな人や音、場所、他の犬と触れ合う経験を積ませておくことで、成長後のトラブルを未然に防ぐことができます。社会化が不十分なまま成犬になると、来客に対して吠えたり、外で他の犬とすれ違うだけで過剰に反応したりと、生活の中で不安が多くなってしまいます。逆に、子犬のうちから“これは怖くない”“これは楽しい”というポジティブな経験を積んでおくことで、自信のある落ち着いた性格に育ちやすくなります。
例えば、抱っこして近所を歩いたり、優しい友人に触れてもらったり、日常の生活音に慣らしたりと、できるだけ多様な刺激を「楽しい体験」として結びつけていくことがポイントです。もちろん、無理やり怖がる状況に置くのではなく、愛犬のペースを尊重しながら少しずつ進めることが大切です。
社会化は一度に終わるものではありませんが、特に生後3ヶ月前後の“吸収力が高い時期”に積極的に取り組むことで、その後のしつけや生活のしやすさに大きな違いが出てきます。安心して過ごせる土台をつくるという意味でも、早期の社会化はしつけの基本中の基本といえるでしょう。
音や環境に少しずつ慣らす
この犬種はもともと繊細な性格を持ち、突然の音や見慣れない場所に対して過剰に驚いたり、不安を感じたりする傾向があります。ですので、日常生活で出会うさまざまな刺激に慣れさせることが、落ち着いた性格に育てるうえでの基盤になります。たとえば、掃除機の音やドライヤーの風、車の通行音など、家庭内外にある「よくあるけれど不快に感じやすい音」は、子犬の頃から少しずつ聞かせて慣らしていくと安心です。最初から大きな音を長時間聞かせるのではなく、小さな音量から始めて、徐々に音の大きさや時間を増やすようにします。
また、散歩コースを時々変えてみるのも効果的です。はじめての道や場所に連れて行くことで、視覚や嗅覚にも刺激が入り、環境の変化に柔軟に対応できるようになります。ただし、無理に引っ張ったり強制的に進めたりすると、かえってトラウマになってしまうことがあるため、犬の様子を見ながらペースを合わせてあげましょう。
静かな環境で学ばせる
この犬種は感受性が豊かで、周囲の刺激に敏感に反応しやすいため、騒がしい場所や人の多い環境では集中力が散漫になりがちです。落ち着いた静かな空間でトレーニングを行うことで、犬が安心して指示に耳を傾けやすくなり、スムーズに学習が進みます。例えば、初めてのトレーニングや新しいコマンドを教えるときには、家の中の静かな部屋を選ぶとよいでしょう。外からの騒音や他の犬の声が聞こえる環境だと、イタリアングレーハウンドは不安を感じたり、気が散ってしまったりすることがあります。静かな環境ならば、飼い主の声がはっきりと届き、コミュニケーションが取りやすくなります。
また、落ち着いた場所でトレーニングを繰り返すことで、犬にとって「ここは学びの時間だ」と認識させやすくなります。この習慣づけは、しつけの成功率を高めるだけでなく、犬自身のストレス軽減にもつながります。逆に、騒がしい場所で無理にトレーニングを続けると、犬が疲れてしまい、しつけ自体が嫌いになってしまう恐れもあるため注意が必要です。
さらに、静かな環境でのトレーニングは、イタリアングレーハウンドが持つ繊細な性格に寄り添うという意味でも大切なポイントです。
排泄トレーニングは根気強く行う
この犬種は性格が繊細で、環境の変化やストレスに敏感に反応するため、トイレの習慣を身につけるまでに時間がかかることがあります。焦らずに根気よく取り組むことで、失敗があっても飼い主との信頼関係を損なわず、スムーズにしつけが進むでしょう。最初のうちは失敗することも多いですが、そのたびに叱るのではなく、成功したときにしっかりと褒めることがポイントです。例えば、決まった場所で排泄できたら「いい子だね」と優しく声をかけたり、おやつを与えたりしてポジティブな体験と結びつけます。これにより、犬は「ここですると嬉しいことがある」と理解し、トイレの場所を覚えやすくなります。
また、決まった時間にトイレに連れて行く習慣をつけることも重要です。食後や起床後、遊んだあとなど、排泄しやすいタイミングを見極めて声をかけることで、犬のリズムを掴みやすくなります。定期的に声をかけることで、「トイレに行くタイミング」を犬自身が認識できるようになるのです。
イタリアングレーハウンドは精神的な影響を受けやすいため、失敗しても怒らず、落ち着いて対応することが肝心です。飼い主が根気強く続けることで、徐々に正しい場所での排泄が習慣化し、生活の質も向上します。
散歩や遊びの時間を確保する
この犬種は元々活発で運動能力が高く、日々のエネルギーを適切に発散させることが心身の健康維持に直結します。十分な運動が不足すると、ストレスが溜まりやすくなり、その結果として問題行動やいたずらが増える可能性が高まります。毎日の散歩は、単に運動するだけでなく、犬にとって新しい刺激や経験を得る大切な時間でもあります。外の世界でさまざまな匂いを嗅ぎ、人や他の犬と触れ合うことで社会性も育まれます。遊びの時間を設けることも同様に重要で、特にボール遊びや軽い引っ張り合いなど、飼い主と一緒に楽しむことで、犬との絆が深まるとともに、良いコミュニケーションのきっかけになります。
イタリアングレーハウンドはその繊細な性格から、不足する刺激に対して敏感に反応することが多いので、遊びや散歩での適度な発散は精神的な安定にもつながります。逆に、運動不足のままだと体力が有り余り、集中力が落ちるため、しつけの効果も半減してしまうことがあります。
また、運動を取り入れたしつけの時間は、犬にとって楽しいだけでなく、学習意欲を高める良い機会にもなります。体を動かしながらのトレーニングは、指示に対する反応も良くなり、無理なくルールを覚えていくことができるでしょう。
お留守番は少しずつ練習させる
この犬種は飼い主に強い愛着を持ち、甘えん坊な性格であるため、急に長時間ひとりにされると不安やストレスを感じやすい傾向があります。そのため、無理なく安心してひとりで過ごせるように、段階的にお留守番の時間を延ばしていくことがポイントとなります。まずは数分から始めて、短時間の離れる練習を繰り返します。最初は飼い主の姿が見えなくなるだけでも不安になることがあるので、できるだけ穏やかに出かけるように心がけましょう。飼い主が帰ってきたときは、落ち着いた態度で迎え、過剰に大げさに喜びすぎないことも大切です。そうすることで、犬は「ひとりの時間は特別なものではない」と理解しやすくなります。
また、お留守番中に安心できる環境を整えることも大切です。お気に入りのおもちゃや、安心できるブランケットを用意したり、音楽を流すなどリラックスできる工夫を取り入れましょう。これらは犬の不安を和らげる助けとなります。
体を触ることに慣れさせる
この犬種は被毛が短く、体が繊細なため、触られる感覚に敏感であることが多いです。そのため、子犬の頃から優しく体を触る習慣をつけておくことで、健康管理や日常ケアがスムーズに行えるようになります。例えば、ブラッシングや爪切り、耳掃除などのケアは、体に触れることに慣れていないと抵抗を示すことがあります。しかし、幼いうちから触ることに慣れていれば、こうしたケアもストレスなく受け入れやすくなるため、病気の早期発見や快適な生活に役立ちます。
触れ方のポイントは、無理強いせず、優しい手つきで行うことです。嫌がったら無理に続けず、一旦やめて落ち着かせることを繰り返すことで、犬自身が「触られても怖くない」と理解していきます。また、触れた後には褒めたりおやつをあげたりして、良い経験として結びつけることも効果的です。
さらに、日常生活の中で散歩の前後や遊びの合間など、リラックスしているタイミングに触る習慣をつけると、自然と受け入れやすくなります。イタリアングレーハウンドの繊細な心に配慮しながら、ゆっくり丁寧に慣らしていくことが、信頼関係を深めることにもつながるでしょう。
無理強いしない
この犬種は繊細で感受性が豊かであるため、強引に命令を押し付けたり、無理に行動させようとすると、ストレスを感じてしまい、かえってしつけがうまくいかないことがあります。優しく寄り添いながら、犬のペースに合わせて進めることが信頼関係を築く鍵となります。例えば、新しいことを教えるときやトレーニングをする際に、犬が戸惑ったり怖がったりしている場合は、一旦休憩を挟むなど無理せず様子を見ましょう。無理強いすると犬が嫌悪感を抱き、飼い主の指示を避けるようになる可能性もあります。イタリアングレーハウンドは、安心感を持てる環境でこそ力を発揮し、しつけもスムーズに進みます。
また、叱る際も強く叱りつけるのではなく、なぜダメなのかを静かに伝えることが大切です。怒鳴ったり身体的に制止することは逆効果となり、犬の自信を失わせてしまうこともあります。代わりに、良い行動をしたときはたっぷり褒めて、ポジティブな関係を築くことを心がけましょう。
しつけは長期戦であり、一気に成果を求めすぎないこともポイントです。イタリアングレーハウンドの気持ちに寄り添いながら、ゆっくりと根気よく続けることが、最終的には良い結果をもたらします。
クリッカーなどの陽性強化ツールを活用する
この犬種は感受性が高く、ポジティブな刺激に反応しやすいため、クリッカーの「カチッ」という音を使って良い行動を明確に伝えることで、学習意欲を引き出しやすくなります。陽性強化とは、犬が望ましい行動をした際に褒めたりご褒美を与えたりして、その行動を強化するトレーニング方法です。クリッカーはそのタイミングを正確に知らせるツールとして非常に優秀で、「今の行動が正解」というサインを瞬時に伝えられるため、イタリアングレーハウンドの理解が早まります。
例えば、「おすわり」ができた瞬間にクリッカーの音を鳴らし、すぐにおやつを与えると、犬は「おすわりをすると良いことがある」と学習しやすくなります。この明確な報酬システムは、叱るしつけとは違い、犬のストレスを減らしながらポジティブに行動を促せるため、信頼関係の構築にも役立ちます。
また、クリッカーは小さな成功体験を積み重ねるのに適しており、複雑なコマンドや新しいトリックを教える際にも有効です。イタリアングレーハウンドの繊細な性格を尊重しつつ、楽しくトレーニングできる環境を作るために、陽性強化ツールの活用はおすすめの方法と言えるでしょう。
日常の中で自然にしつけを行う
この犬種は賢く感受性も豊かですが、特別なトレーニング時間だけでなく、普段の生活の中で繰り返しルールを教えることで、しつけがより定着しやすくなります。生活のあらゆる場面を活用して、自然な形で学習させることがコツです。例えば、食事の前に「おすわり」をさせる、散歩のときにリードを引っ張らないように声をかける、来客時には落ち着いて挨拶させるなど、日々の行動の中でしつけを取り入れていく方法です。こうした繰り返しの積み重ねが、犬にとって「こうするのが普通」という習慣となり、無理なくルールを守れるようになります。
また、イタリアングレーハウンドは環境の変化や新しい刺激に敏感なため、日常の中で様々な場面を通じて経験を積ませることが精神的な安定にもつながります。たとえば、散歩で通る場所や訪れる人が変わっても、基本的なマナーを守らせる練習をしておくことで、どんな状況でも落ち着いて行動できるようになるのです。
さらに、日常生活でのしつけは、飼い主と犬とのコミュニケーションを深める良い機会でもあります。声のトーンや褒め方を工夫しながら、楽しく続けられることが、イタリアングレーハウンドの信頼と理解を促進します。特別な時間だけでなく、毎日の暮らしの中でしつけを意識的に取り入れることで、より良い関係が築けるでしょう。
まとめ
今回は
イタリアングレーハウンドのしつけのコツ
についてのお話でした。
以上の見解がお役に立てたのであれば幸いですが、もし解決に至らないようであれば、犬のしつけプロのノウハウや手厚いサポート付きのマニュアルを是非チェックしてみてください。
■是非読んでほしい必読情報
以上の見解がお役に立てたのであれば幸いですが、もし解決に至らないようであれば、犬のしつけプロのノウハウや手厚いサポート付きのマニュアルを是非チェックしてみてください。
■是非読んでほしい必読情報